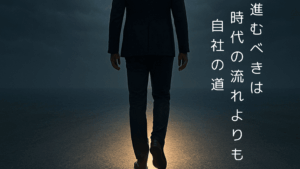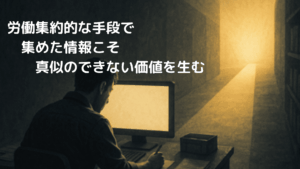ロジカルな人ほど抜け出せない「売れないメカニズム」
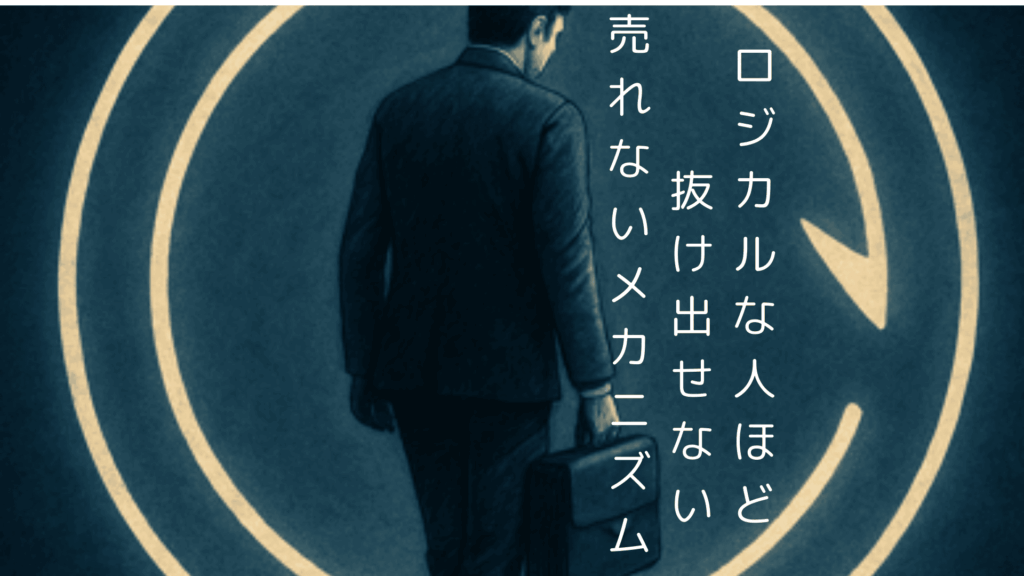
現場作業は、理詰めの世界です。
そのため、倉庫業・作業請負業の責任者には、ロジカルな方が多いです。
しかも、そういうロジカルな人ほど陥りやすい罠があります。
それは「売れないメカニズム」から抜け出せない症状です。
「うちのサービスは、機能的に優れている」
「なのに、なかなかその良さを分かってもらえない。なんで!?」
これは、営業や企画の現場でよく聞く嘆きの言葉です。
特にロジカルな人ほど、「論理的に正しいのだから、相手も納得するはずだ」と信じて疑いません。
しかし現実には、どんなに理屈を積み上げても売れないケースに直面してばかりです。
むしろ、論理的に説明しすぎて、かえって相手の気持ちが動かないという状況さえ起きます。
この“売れないメカニズム”には、ある盲点があります。
それは、「買う」という意思決定は、理屈ではなく“感情”や“直感”から始まるという事実です。
裁判官が教えてくれた、“決め方”の本質
私は若い頃、法律を学んでいた時期があります。
特に刑法は、ある意味で数学のようなものだと感じていました。
まず事実を認定し、その事実に対して法律を適用する。曖昧な部分は解釈によって埋めていく。論理の積み上げによって結論を導く、まさに理詰めの世界だと。
ところが、その理解が根底から覆された出来事がありました。
ある裁判官の話を聞いたときのことです。
その裁判官は、事件を俯瞰してまず「直感で結論を決める」のだと言います。
そして、その“筋”に対して、事実や法律を当てはめていく。
事実や条文の解釈は、その直感を検証したり、補強したりする役割に過ぎない、と。
さらに驚いたのは、直感に反する場合、法解釈を変えることすらあるということでした。
「法律の世界は理屈がすべて」という私の思い込みは、180度覆されました。
感情と理屈には順番がある
この考え方は、営業にもそのまま当てはまります。
人は、目の前の状況から限られた情報をもとに、まず“直感的に”判断します。
「これは良さそうだ」「なんか違う気がする」
その第一印象が、実は意思決定の核心部分になっています。
理屈は、その判断を正当化するために後から使われるに過ぎません。
つまり、理屈や機能をいくら並べても、相手の“買う”という気持ちは動かせないのです。
順番が逆なのです。
感情に訴えかける2つの方法
では、どうすれば“感情”を動かすことができるのか?
私は次の2つの方法を、実践の中で学びました。
① ストーリーで語る
人の感情は、ストーリーに反応します。
これにはパターンがあって、とくに「苦労→努力→失敗→再挑戦→成功」という流れは、誰の心にも響きます。
映画『ロッキー』をご存じですか?
冴えない三流ボクサーが、不遇な状況から一度は自暴自棄になる。
しかし、世界戦のチャンスをつかみ、恋人の助けを受けて、努力と根性で這い上がる。
結果がどうあれ、その姿に人は心を動かされます。
自社のサービスも、『ロッキー』のストーリーに乗せてみてはどうでしょうか。
「最初は社内でも反対だらけ。スタートを切っても失敗ばかり。『それ見たことか』という声が聞こえてきた。でも、諦めずに改善を重ねた。その結果、理解してくれる仲間が少しずつ増えた。そしてようやくここまで来た」
このように、自社がこのサービスにどんな想いを込め、どんな困難を乗り越えてきたのかを伝える。
それだけで、サービスは「商品」から「人間の営み」へと変わります。
相手の感情が動く瞬間です。
② ネガティブな期待に応える
もうひとつ大切なのは、相手の不安に寄り添うことです。
営業先が法人であれば、商談相手には次のような心理があります:
- 「この業界に詳しい業者に任せたい」
- 「上司にちゃんと説明できる材料がほしい」
- 「業者を比較するのが面倒。絞りたい」
- 「自分が推進したことで失敗したくない」
人は、何を得ることよりも、何かを失うことに心が大きく反応します。
こうした“ネガティブな期待”に対して、先回りして言語化し、こちらから解決策を提示するのです。
たとえば:
- 「新しい仕組みは社内で反発されやすい。だからこそ導入事例を具体的に提示します」
- 「価格だけで比較されがちですが、リスクや柔軟対応の差は、あとで大きな違いになります」
- 「比較検討が面倒なのは分かります。必要な判断材料は、こちらで一覧にしてお渡しします」
こう伝えることで、「この会社は分かってくれている」「頼れそうだ」と相手は感じる。
つまり、理屈の前に“安心”を得られるのです。
ロジックだけでは売れない理由
ロジカルな人ほど、「売れない理由」に気がつかずに、どんどん深みにはまっていきます。
データを増やし、スペックを補強し、理屈を整える。
でも、それでは売れません。
なぜなら、顧客の感情が動いていないからです。
まずは相手の心に火をつける。
少しついたその火を、理屈で安定させる。
この順番こそが、“売れる仕組み”だといえます。
「売れないメカニズム」から抜け出すには、
「人は直感で決め、理屈で正当化する」という前提に気づくことが第一歩です。
相手の感情にどう寄り添うか、
自社のストーリーをどう語るか、
相手の不安にどう応えるか。
ここを考え抜いていくと、驚くほど呆気なく、貴社のサービスが売れるときが訪れるでしょう。
.png)