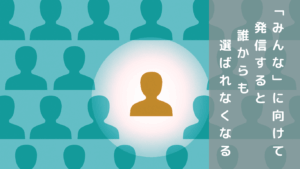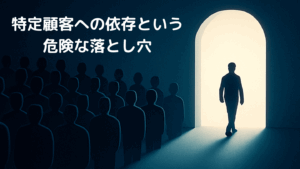新規事業を評価するとき、絶対にやってはいけないこと
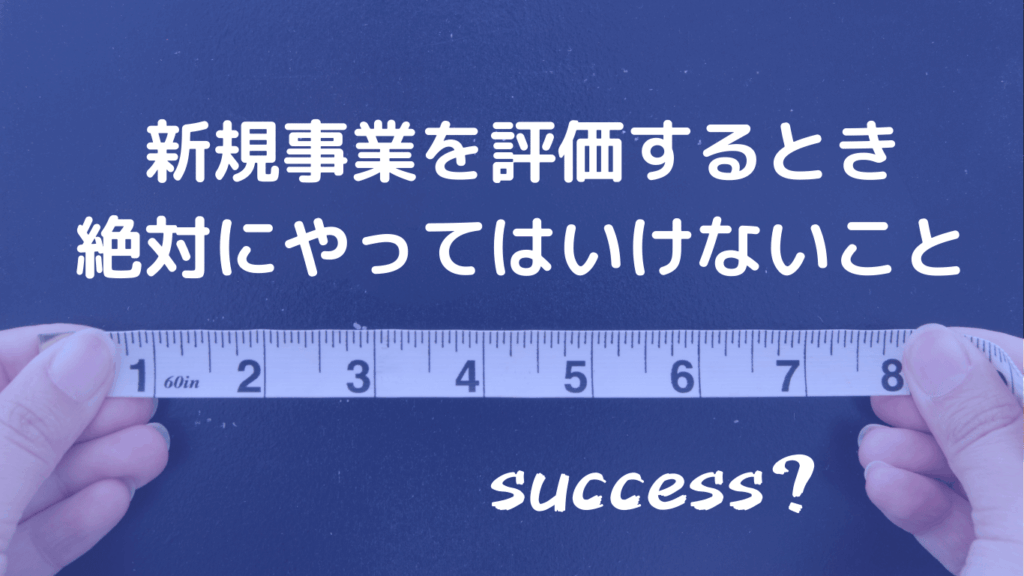
「いつもの物差し」で測る危険
新しい事業を立ち上げたとき、誰もがやることがある。それは、パフォーマンスの評価だ。
収益は上がっているか。コストは適正か。利益率はどうか。
こうした問いかけ自体は正しい。しかし、ここで大きな間違いを犯してしまう経営者は多い。
それは、既存事業と同じ物差しで、新規事業を測ろうとすることである。
この罠に気づかないまま突き進むと、せっかく立ち上げた新規事業を自ら潰してしまう危険がある。
「倉庫業の常識」が通用しなかった実体験
かつて私は、倉庫を活用した一般消費者向けの収納代行サービスを立ち上げた。
法人荷主向けが主流の倉庫業界において、個人向けに舵を切った新しい挑戦だった。
当然、色々な苦労があった。オペレーションの違い、顧客対応の違い、そして何より困ったのがパフォーマンスの評価基準である。
当時、私が所属していた会社では、倉庫業の常識どおり、「利用スペースあたりの売上総利益・営業利益」で事業を評価していた。
しかし、周辺の競合事業者と話をするうちに、ある衝撃の事実に気づいた。
彼らはそんな指標では測っていなかったのである。
彼らが重視していたのは、投資金額に対する利回りだった。
もっと言えば、減価償却費も営業経費もあまり気にしていなかった。
要するに、倉庫スペースを不動産の一部として貸し出す「不動産業」をやっていたのだ。
私は倉庫業として採算を取ろうと必死だったが、競合は不動産業の常識で動いていたのである。
この「ズレ」は致命的だった。
間違った物差しが、事業を壊す
こちらは倉庫業の常識に従って、コストを細かく積み上げ、営業利益を厳格に見ていた。
結果、競合と比べて価格を高く設定せざるを得ず、競争力を失い、戦略の変更を余儀なくされた。
社内では「利益が出ていないから失敗」と評価され、事業継続そのものに疑問符がつけられた。
これは単なる失敗談ではない。
もし競合と同じ「利回り基準」で見ていれば、事業は十分成立していたのである。
評価の物差しを間違えただけで、実態とは異なる判断が下される――これが新規事業の怖さだ。
そして、さらに深刻なのは、このズレが社員のモチベーションを徹底的に壊すことである。
現場で必死に顧客を獲得し、サービスを改善しようと努力しているのに、「利益が出ていないからダメだ」というレッテルを貼られる。
こんな理不尽なことがあるだろうか。
参入先の常識を見抜くための3つのポイント
では、新規事業を正しく評価するためにはどうすればいいのか。
そのためには、参入先の常識を見抜くことが欠かせない。
具体的には、次の3つのポイントがある。
1. 競合企業のKPIを探る
まずは、競合となる企業が何を重視しているのかを探るべきである。
売上高か、利益率か、あるいは投資回収期間か。
彼らが社外向けに発信している情報、求人票、営業資料などから、意外とヒントは拾える。
そういった資料がないならば、直接会って勉強させてもらってくればよい。
競合の担当者と雑談を交わすなかで、どんな数値を重視しているのか、さりげなく探ってみることだ。
こうして得られる情報は、非常に貴重なものになる。
2. 参入市場のビジネスモデルを理解する
次に、その市場特有のビジネスモデルを理解する必要がある。
たとえば、不動産業であれば「利回り」、サブスクリプション型であれば「LTV/CPA」、EC事業なら「広告費率」など、
業界ごとに常識となっている評価指標は異なる。
ここを押さえずに進めると、見えない地雷を踏むことになる。
3. 自社にとっての「生きた基準」を設計する
最後に重要なのは、参入市場の常識をそのまま丸呑みするのではなく、
自社のリソースや戦略に即した評価基準を設計し直すことである。
たとえば、競合が高リスク前提で利回りを追求しているなら、
自社は低リスク前提で利益率を重視するという考え方もある。
大切なのは、参入市場のルールを理解したうえで、自社なりの合理的な評価軸を持つことだ。
最後に
新規事業のパフォーマンス評価は、既存事業の物差しで測ってはならない。
参入先の常識を読み解き、自社なりの生きた基準を設計すること。
これができなければ、せっかく芽吹いた事業を、自らの手で摘み取ってしまうことになる。
そして――。
評価基準の設計こそ、新規事業立ち上げ時に最初に手を付けるべき「見えない設計図」である。
この設計を誤らないために、どんな準備をすべきか。
それについては、また別の機会に詳しく掘り下げたい。
.png)