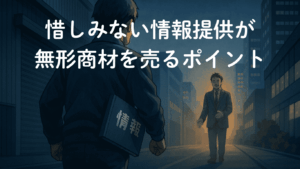両利きの経営は中小企業にも本当に有効か?~新規事業を生み出す“もう一つの答え”~

「両利きの経営」をご存じですか?
こんにちは。
この記事を読んでくださっているあなたは、おそらく中小企業の経営者や役員の方ではないでしょうか。
日々、現場をまわしながら、「このままでいいのか?」と将来の成長に不安を感じているかもしれません。
そんなあなたに、今日は少し「両利きの経営」という考え方についてお話ししたいと思います。
これは、チャールズ・オライリーという経営学者が提唱したもので、既存事業を深掘りして利益を生み出す「深化」と、新しい市場を切り開く「探索」の両方を同時に進めることが大事だ、という理論です。
なるほど、たしかに大事な話です。
でも、あなたはこう思いませんか?
「うちは中小企業。そんなに人もいないのに、両方やるなんて無理だよ」と。
はい。実は、私もまったく同じことを感じていた一人でした。
現場で感じた違和感~理論と現実のギャップ~
私は20年にわたり、物流業界で新規事業の立ち上げをしてきました。
最初は現場の一社員として、そして途中からは事業責任者として、新しいサービスをゼロからつくり、売って、軌道に乗せるまでのすべてを担当してきました。
新しいアイデアを思いつく。
それを企画書にまとめる。
現場でテストをして、営業に回る。
お客さんから「いいね!」という声を聞く。
導入が決まると、今度はオペレーションの仕組みを作る。
しばらくしたら、また次のアイデアを探し始める。
まさに、「深化」と「探索」をぐるぐると回していたわけですが、それを支えていたのは、ほんの数人の「何でも屋」でした。
どちらかに特化する余裕など、ありませんでした。
だからこそ、私は思ったのです。
「この“両利きの経営”って、本当に中小企業にとって現実的なのか?」と。
小さな組織にとって「探索」が難しい3つの理由
小さな組織が「探索」、つまり新しいことにチャレンジするのが難しいのには、いくつか理由があります。
私の経験から、その中でもとくに大きな理由を3つに絞ってお伝えします。
①既存事業に精通していないと意味がない
新しいことを始めるといっても、それは「今までとはまったく違うこと」ではありません。
むしろ、今ある業務・サービス・顧客の中に、まだ見えていない“課題”を見つけることがスタートです。
だから、「探索」には既存業務への深い理解が必要になります。
ところが、探索担当を分けようとすると、どうしても「社内の事情を知らない人」に任せることになりますよね。
これでは、せっかくのアイデアも現場に届かず、実現されません。
②人がいないから、片手間で「探索」
「探索」に特化したチームを作りたくても、そもそも人がいない。
これは、小さな組織が抱えるリアルな課題です。
実際、私がいた組織でも、少人数で既存業務を回すのがやっとでした。
「ちょっと余った人員で新規事業を…」というわけにもいかない。
だから、必然的に“片手間でやるしかない”状況が生まれるのです。
③失敗のリスクが大きすぎる
大きな組織と違って、小さな組織にとっては、一度の失敗が命取りになることがあります。
新しいことに人とお金をつぎ込んで、それが失敗したら、既存事業にまで悪影響が出る。
だから、失敗できない。
だから、リスクが取れない。
結果として、探索が進まない。
このジレンマに、多くの経営者が頭を悩ませているのではないでしょうか。
それでも、「探索」を止めてはいけない理由
とはいえ、「探索」をやめてしまえば、成長の芽が摘まれてしまいます。
変化の激しい今の時代、既存事業だけに頼るのはリスクそのもの。
では、どうすればいいのでしょうか?
ここからは、私のこれまでの経験から学んだ「小さな組織なりの探索のやり方」についてお話ししたいと思います。
小さな組織の探索は「ある特定の顧客」から始まる
私がたどり着いた一つの答えは、
“探索は、身近な「ある特定の顧客」に徹底的に向き合って、「未解決の困りごと」に耳を澄ますことから始まる” ということです。
「社会がこう動いているから」
「業界のトレンドはこうだから」
「最新テクノロジーが現われたから」
こういった“広い視野”ももちろん大切ですが、実際に行動を起こすときには、もっとミクロな「目の前のお客様」に集中することが成功のカギになると感じています。
あなたの会社にも、長年付き合っているお客様がいるのではないでしょうか?
そのお客様は、あなたの会社を信頼してくれています。
だからこそ、「実はこんなことに困っていてね…」という話を、してくれる可能性があるのです。
「深化」は「探索」の延長線上にある
「探索」は既存事業、「深化」は新規事業と、完全に分けようとすると、小さな組織ではどうしても無理が生じます。
むしろ、既存事業を進めながら、その時々で「深化」を意識しながら、
「これは他のお客様にも使えるかもしれない」
「この作業は別の分野でも展開できるかもしれない」
という“発見”があったときに、探索へとつなげていく。
これが現実的なやり方です。
たとえば、倉庫業なら「ある製品の保管」業務をしていたとします。
そこで既存顧客にヒアリングをして分かったキッティング、検査などの「前後の工程」に着目すると、新しいサービスのヒントが生まれるかもしれません。
このように、「深化」と「探索」は切り離すものではなく、“地続き”であると考えたほうが、無理がありません。
「片手間探索」は悪じゃない。むしろ戦略です。
「探索を片手間でやっているなんて、甘い」と言われることがあります。
でも、私は声を大にして言いたいのです。
小さな組織においては、「片手間探索」こそが、最も現実的で、最もリスクの少ない成長戦略です。
片手間だからこそ、失敗しても痛みが少ない。
片手間だからこそ、既存の知識や人脈を使って効率よく仮説検証ができる。
そして何より、実現可能性の高いアイデアに絞り込まれていくのです。
まとめ:あなたの会社ならではの探索を
「両利きの経営」は、確かに立派な考え方です。
でも、現場を知り尽くした経営者として、あなたが求めているのは「理論的な正しさ」ではなく「現実に使える知恵」ではありませんか?
中小企業の探索は、決して「大胆に新しいことをやる」ことではありません。
むしろ、「いまある顧客との関係のなかに、まだ見ぬ価値を見つける」こと。
それなら、きっとあなたにもできるはずです。
あなたの会社ならではの“探索のしかた”、一緒に考えていきませんか?
.png)