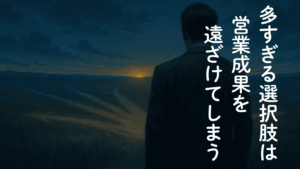食品スーパーの社長に教わった、営業の極意 ~「売り時」起点の営業戦略~

電力会社時代の、忘れられない出会い
私は、大学を卒業してから20代のあいだ、ある電力会社で働いていました。
当時の配属先は「高圧」と呼ばれる、中規模事業者向けに電力契約の提案をする仕事です。
工場や病院、商業施設などの電力使用状況を分析し、最適な契約種別や契約電力の更新を行うのが私の主な役割でした。
その中で、私が特に力を入れていたのが、「エコアイス」という氷蓄熱式空調の導入促進です。
これは、深夜の安い電気で氷をつくり、その冷熱を日中の空調に活用するシステムで、ピーク電力の平準化に効果があるとされていました。
ある日、私は地域に10店舗以上を展開する食品スーパーを訪問しました。
案内された先には、なんと社長ご本人が待っていました。
「これはチャンスだ」と意気込んだ私は、資料を片手に、エコアイスの仕組みや電気代の削減効果について一生懸命に説明しました。
ところが、その社長は私の話を静かに聞いた後、諭すようにこう言ったのです。
「君の上司は、こういう提案をしてこいって言ってるの?それだと絶対に売れないから、上司に言った方がいいよ。」
社長からの痛烈な一言
思わぬ言葉に戸惑う私に、社長はさらに続けました。
「既存の店舗には、もう普通のエアコンがついてる。あとから氷をつくる設備を足すなんて現実的じゃないんだよ。」
私は思わず固まりました。
「こういう提案をするなら、新しい店舗を出すときの設計段階でやるべきだ。提案相手はうちじゃなくて、設計事務所だな。」
そして最後に、少しだけ優しい声でこう言ってくださいました。
「普通なら、こんな営業は無視するか追い返すけど、君みたいな若いのには教えておくよ。上司にちゃんと伝えなさい。」
私はその日、自分の未熟さを痛感しました。
「言われた通りの営業」をしていた私に、社長は「お客様の立場に立って、自分の頭で考えろ」という当たり前でいて、本質的な視点を教えてくれたのです。
「売り時」と「売り先」を見誤ってはいけない
この経験を通じて、私は営業における最も重要な視点を学びました。
それは──
**「求めている人のところへ、求めているときに行く」**ということです。
どんなに素晴らしい商品・サービスであっても、必要とされていない相手に届けても、売れません。
さらに言えば、「今は必要ない」と思われているタイミングでアプローチしても、相手の心は動きません。
たとえば、冷たいミネラルウォーターも、真冬の寒い日にはなかなか売れませんが、真夏の炎天下であれば飛ぶように売れます。
同じ商品でも、「売り時」と「売り先」によって、反応がまったく違うのです。
逆に、ここさえ間違えなければ、営業は驚くほど楽になります。
「このサービス、ちょうど探していたんだよ!」という言葉が返ってくる。
これほど心強いことはありません。
では、どうすればその「売り時」をつかむことができるのでしょうか?
法改正は、最大の売り時である
私が営業戦略を考えるうえで、真っ先にチェックするのは「法改正・制度改正」です。
なぜなら、法改正には〝強制力〟があるからです。
例えば近年では、インボイス制度の導入や電子帳簿保存法の改正などがありました。
あなたの会社でも、「対応しなきゃいけない」と急いで動いた経験があるのではないでしょうか?
法改正の良いところは、「どうしてもやらなきゃいけない」という圧力があるため、ニーズが顕在化していることです。
このタイミングで必要な機能・サービスを提示できれば、「導入しない理由がない」状態をつくれます。
物流業界でいえば、2024年には「物流の2024年問題」として、トラックドライバーの労働時間規制が始まりました。
このタイミングで、ドライバーの運行時間管理、荷待ち削減のためのバース予約システムに関するツールやサービスのニーズが一気に高まりました。
営業は、こうした「法律・制度改正の波」に乗るのが最も効果的です。
努力の方向性が正しければ、少ない力で成果を得ることができます。
社会ニーズの変化に寄り添う
もう一つの「売り時」は、社会的なニーズの変化です。
原価の高騰、人手不足、働き方改革、DX推進、AI活用…。
これらはすべて、企業にとって避けられない課題であり、そこにソリューションを提供できる企業は強い味方として歓迎されます。
あなたの会社でも、こうしたニーズを感じる瞬間があるのではないでしょうか?
では、自社のサービスや強みが、これらの社会課題にどう役立つかを、きちんと説明できますか?
社会ニーズを把握するには、商工会議所や中小企業庁などが開催するセミナーや勉強会のテーマを見るのが有効です。
今、世の中の経営者が「学びたい」と感じている内容こそ、ホットな課題の証拠です。
PCB廃棄物処理の営業から得た教訓
これは、私が物流会社で新規サービスを立ち上げたときのことです。
ある制度変更のタイミングで、廃棄物収集運搬の新規事業を立ち上げました。
それは、古い変圧器やコンデンサーに含まれていた有害物質「PCB」の処理制度が開始された時期のこと。
各地で処分施設が整備され、全国の事業者に対して「処分してください」という通達が出されていました。
ですが、実際には「自分がPCBを保有していることすら知らない」「どうやって処分すればいいかわからない」という会社が多く存在していました。
そこで私は、制度の概要、手続きの流れ、対応しない場合のリスクなどを分かりやすくまとめた資料を作り、DMとして送りました。
それだけです。営業トークも値引き提案もしていません。
にもかかわらず、「うちにもあるみたいなんだけど、詳しく説明してほしい」という連絡が、次々と届きました。
それまで物流サービスをそのまま売ろうとすると門前払いをされていたような先から、「是非、説明にきてほしい」という依頼が多くきたのです。
制度改正という「売り時」と、情報提供という「売り方」が見事に合致した結果でした。
あなたの営業は、どのエスカレーターに乗っていますか?
営業には、「下りエスカレーター」と「上りエスカレーター」があります。
努力しても成果が出ないのが前者で、自然に成果がついてくるのが後者です。
そして、どちらに乗るかは、「売り時」と「売り先」を正しく選べているかどうかで決まります。
苦労することが大事なのではなくて、いかにして苦労せずに結果を出すかが大事なわけです。
倉庫業、運送業、作業請負業──。
今の時代、これらの業界もまた、変化の波にさらされています。
もし、いま自社のサービスが売りにくいと感じているなら、それは「タイミング」がズレているだけかもしれません。
あなたの商品が悪いわけでも、営業の腕が悪いわけでもない可能性があります。
まずはやってみて欲しいこと
この記事でお伝えしたかったのは、「売り時」から逆算して営業戦略を立てるという考え方です。
これは、私が若い頃に食品スーパーの社長から教わった、営業の本質とも言えるものです。
ぜひ、次の商談、次の提案、次の事業構想を考えるときには、こう問いかけてみてください。
「これは、今、誰にとって必要なのか?」
法改正や制度改正の情報を調べて、あなたの会社のサービスがどこにどう役に立つかを考えてみてください。
この問いが、あなたの営業活動に新たな風を吹き込むヒントになれば幸いです。
.png)