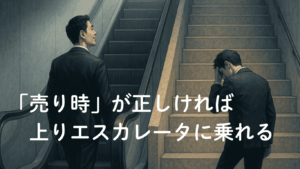“何でもできます”では伝わらない ~物流業・作業代行業のための「選ばれる提案」の工夫~
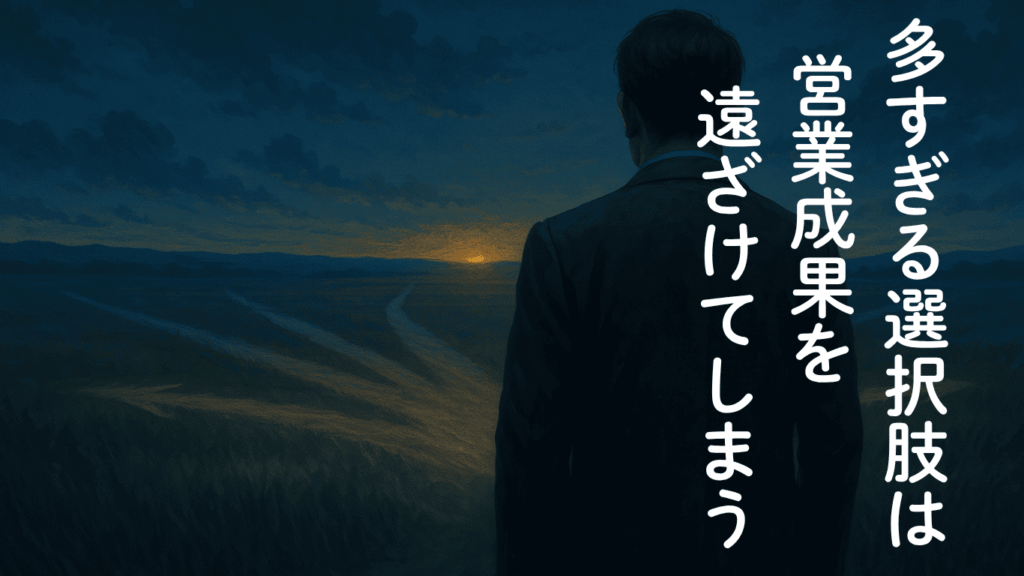
なぜ『松竹梅』の提案が有効なのか
営業先で提案をするとき、いくつかのプランを並べて提示すること、ありますよね。
たとえば、すべての要望を満たすけれども時間もコストもかかる提案、必要最小限の対応だけれどもすぐに実行できて安価な提案、その中間に位置するバランス型の提案。
――いわゆる「松竹梅」スタイルの提示方法です。
私自身、何度となくこのスタイルで提案してきましたが、やはり顧客の反応はよいのです。
「A案はちょっと重いけど理想だな、でもC案じゃ物足りない、B案でいこうか」といった具体的な比較・検討が始まりやすい。
お客様が「決めやすい」というのもありますが、具体的な選択肢を出すことでイメージしていただくことができ、そこから議論が始められます。
お客様の「本音」を引き出すきっかけになりやすいわけです。
この「松竹梅方式」は、実は感覚的に行われてきたものではありません。
行動経済学的にも裏付けのある、非常に有効な手法なのです。
選択肢が多すぎると人は決められない
人は「選べること」が好きなように見えて、実は「選びたくない」と感じることがよくあります。
選択肢が多すぎると、脳が情報を処理しきれず、意思決定を後回しにしたり、最悪の場合「選ばない」という行動をとってしまいます。
これを「選択のパラドックス」と言います。
行動経済学の有名な概念ですね。
倉庫業や運送業、作業請負業でも、「何にでも対応できます」というサービス説明が、この“選ばれなさ”を招く原因になっていることがあるのです。
「柔軟に対応できます」は、一見すると顧客想いのように見えます。
でも、聞き手が“自分にとって必要な内容”を想像できなければ、それは「何を頼んだらいいか分からない」に変わります。
自由すぎる選択肢が混乱を招く
先日、私はとある人気のカレー店に入りました。
この店では、ご飯の量・辛さ・トッピングをすべて自分でカスタマイズできます。トッピングの種類も非常に豊富で、組み合わせはまさに無限。
でも、私は迷いました。
あれもこれも気になるけど、どれをどう組み合わせたら正解か分からない。
結局、「ポークカレー、ご飯普通、辛さ普通、トッピングなし」という、最もシンプルな選択をしてしまったのです。
自由であることが、逆に私の選択を萎縮させた瞬間でした。
あなたも似たような経験があるのではないでしょうか?
組み合わせ提案で、選びやすく・売りやすく
この経験から私が学んだのは、「自由な選択肢」はときに不親切だということです。
そこで有効になるのが、あらかじめいくつかのセットを組んで提案することです。
たとえば、トッピングセットA(チーズ+目玉焼き)、セットB(ウインナー+野菜)、セットC(から揚げ+卵)といった提案があれば、お客様はその中から「なんとなく自分に合いそうなもの」を選びやすくなります。
この方法は飲食業だけでなく、スマートフォンの料金プラン、自動車のグレード設定、家電のオプション提案など、さまざまな業界で当たり前に使われています。
同じように、物流業・運送業・倉庫業でも、「選択肢を絞って提示する」ことは、売り手・買い手双方にとって多くのメリットをもたらします。
“何でもできます”では誰にも届かない
たとえば「何でも預かります」「どんなものでも運びます」「どんな作業でも代行します」といった訴求。
一見、柔軟性があるように見えます。
でも実際には、誰にも刺さりません。
なぜなら、受け手は「自分に関係あるかどうか」を判断できないからです。
考える手間を相手に押し付けてしまっているんですね。
この状況こそが、選択のパラドックスそのものです。
顧客に「自分ごと化」してもらうには、選択肢や使い方の例を“あえて限定的に”提示する必要があります。
使い方を見せると、想像が広がる
たとえば、ある会社が「取扱説明書のキッティングサービス」というメニューを打ち出しました。
これは、製品マニュアルや保証書、カタログなどを封入して仕分け・納品する作業を一括で請け負うサービスです。
すると顧客からは、「うちは取扱説明書はないけど、販促資料がある」「展示会用のサンプルと一緒にチラシも配りたい」など、連想的なニーズが次々と生まれました。
「キッティングサービス」という名前が、使い方のイメージを伝える役割を果たしたのです。
あなたの会社でも、こういった“イメージしやすい”サービスの見せ方はないでしょうか?
絞ることで、現場も効率化する
さらに、このような具体的な提案を行うことで、現場の効率も格段に良くなります。
同じような作業が集中すれば、教育の手間も減り、ミスも減ります。
作業手順が共通化されれば、標準化・マニュアル化も進みます。
特化によるコスト削減、品質の安定、利益率向上。いいことずくめです。
「どんな仕事でもとる」から「この領域に絞る」へ。
これは、単なる営業戦略ではなく、生産性向上のための合理的な選択なのです。
“売り方”を見直すだけで選ばれる可能性は高まる
どんなに優れたサービスでも、相手がそれを「自分に必要だ」と感じなければ、選ばれません。
物流業・運送業・倉庫業といった業種では、汎用性が高いがゆえに、「用途が分からない」と思われることも少なくありません。
だからこそ、「こんな人に」「こんなときに」「こんな風に使ってほしい」という提案を、こちらから仕掛けていく必要があるのです。
おわりに ~“選ばれ方”を設計しよう
選ばれるためには、選びやすさの設計が必要です。
あなたの会社のサービスが、いま「何でもできます」のままになっていないか――いま一度、見直してみてください。
行動経済学の知見を活かし、選択肢の数や見せ方を工夫するだけで、顧客の反応は大きく変わります。
それは、営業効率だけでなく、現場オペレーションの効率にも波及します。
売上・利益を伸ばすだけでなく、社員のモチベーションや顧客との関係性を変える力をもった“見せ方の工夫”。
あなたの会社のサービスに、あらためて「選ばれる理由」を設計してみてはいかがでしょうか。
.png)