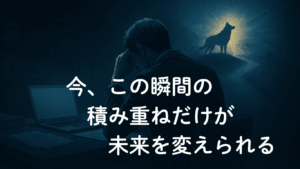価格転嫁交渉を成功させる根拠資料の作り方 ~実践・実証済み~
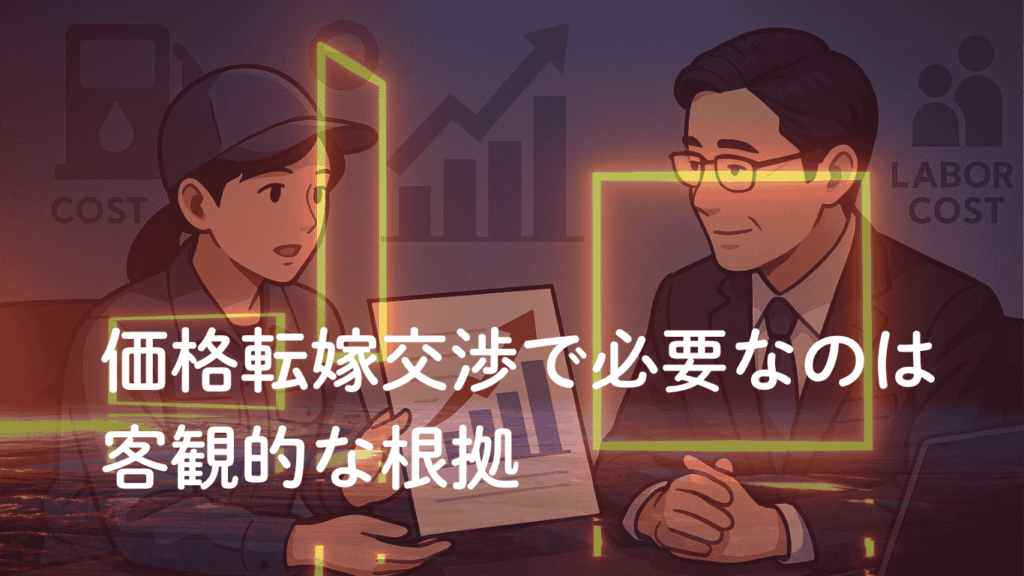
はじめに
原材料費、燃料費、人件費。さまざまな費用が上昇しています。
これまでは生産性の向上・業務の効率化という自助努力で対応してきた会社でも、もはや対応はしきれない状態になっています。
あなたの会社では、価格転嫁は進めていますか?
これから記載する内容は、私自身が実際に価格転嫁交渉を成功させた方法です。
今回はいつもに増して、すぐに役立つ重要な内容になります。
最後までお読みいただけると嬉しいです。
「根拠」を提示することが大事な理由
価格転嫁交渉を進めようとしたときにポイントとなるのは、「根拠」の示し方です。
※価格転嫁の進め方の全体概要については、別記事「中小企業のための価格転嫁交渉の実践方法」をご覧ください。
まず、そもそもなぜ「根拠」が重要なのでしょうか?
それには、人がもともと持つ、ある心理が影響しています。
人は「自分は合理的な存在だ」と思いたがる傾向があり、自分自身のなかで整合性をとって納得する心理をもっています。
これを実際に実験で確かめた研究者がいます。
社会心理学者のエレン・ランガーは、コピー機待ちの列に並ぶ学生に対して、どう言ったら割り込める確率が上がるかを実験しました。
①「すみません、5枚だけなんですが、先にコピーをとらせてもらえませんか?」
②「すみません、5枚だけなんですが、コピーをとらなければならないので、先にコピーをとらせてもらえませんか?」
③「すみません、5枚だけなんですが、理由があるので、先にコピーをとらせてもらえませんか?」
結果はどうだったと思いますか?
承諾率は、①60%、②94%、③93%でした。
どうでしょうか? ②も③も理由らしい理由は言っていません。なのに大幅に承諾率が上がりました。
これは、おそらく依頼を受けた側が「きっと何か深刻な理由があるに違いない」と勝手に想像して、自分自身のなかで整合を取ったからではないでしょうか。
「根拠」は存在するだけで、重要なのです。
価格転嫁交渉で提示するべき「根拠」とは?
とはいえ、価格転嫁交渉においては、いい加減な根拠では納得を得ることは難しいでしょう。
では、どういう根拠を出せばよいのでしょうか?
この点について、多くの方が「原価を把握して、交渉相手に原価上昇を説明せよ」といいます。
でも、私は、実際の原価を交渉相手に提示することは、避けるべきだと考えています。
たしかに、原価を把握しなければ、どの案件がどれだけ儲かっているのか分かりませんし、どれだけ価格転嫁をすれば良いのかも分かりません。
ですから、原価の把握は必須だと私も思います。
しかし、「原価が上がっている」ことを示すのに、あなたの会社で実際にかかっている原価を提示することが有効でしょうか?
交渉相手からすると、こんな疑問が湧いてこないでしょうか?
「そもそも元々の原価に問題があるのではないか?」
「あなたの会社の原価低減努力が足りないのではないか?」
「本当にその原価で正しいのか?」
そうです。
原価が上昇していることは理解できても、「あなたの会社の原価」が適正であるかどうかが分からないのです。
透明性を感じてもらえないので、理解を得にくいのです。
交渉に必要な、相手との「共通の土台」
では、どうすればいいのか?
それは、互いが合意していて、争いのない「共通の土台」の上に立つことです。
そういう「共通の土台」には、2つあります。
一つめは、いますでに締結している契約、つまり現在の料金です。
現在の料金については、相手は納得してあなたの会社のサービスを利用して、お金を払っているわけです。
だから、現在の料金に軸足を置いて交渉するべきです。
もう一つの共通の土台は、世の中に客観的に示されているデータです。
人件費であれば、都道府県ごとに定まっている最低賃金。燃料費であれば、資源エネルギー庁が出している「石油製品価格調査」。
こういった客観データは、交渉相手にとっても争う余地のない透明なものです。
「共通の土台」に立った根拠の示し方
この2つの「共通の土台」に立ったとき、交渉のために具体的にどうやって根拠を示せば良いのでしょうか。
それは、こういう具合です。
人件費を例にとってみます。
現行の料金が決まったとき(契約時点)における最低賃金と、現在における最低賃金を比較するのです。
その増加率を「原価の上昇率」として主張すれば、交渉相手は否定のしようがありません。
例えば、東京都内に事業所があって、現行の契約が2011年10月に締結されていたとしましょう。
東京都の2011年10月時点の最低賃金は837円。この記事を書いている2025年7月時点の最低賃金は1163円。この間の原価上昇率は27%。
つまり、作業料金を27%上げる申入れをすることは、理屈が立つわけです。
同じような考え方で、燃料費、資材費、電気代なども整理していけます。
あとはこれらの理屈によって積み上げた上昇率を加味した金額が、欲しい値上げ幅を上回るように構成していくだけです。

武器となるツール ~原価上昇を説明する資料~
最後に、いざ交渉に臨む際に用意する資料について、お話ししましょう。
もちろん、行政や業界団体の統計情報を調べていっても構いませんが、非常に大変でしょう。
そこで助けになるのが、埼玉県が準備している「価格転嫁交渉ツール」です。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/library-info/kakakukoushoutool.html#download
必要な情報を入力していくだけで、原価の上昇を示すグラフ入りのチラシが作成できます。
資料作成が楽になるというだけでなく、自治体が示した資料ということで説得力も大幅に上がります。
是非、活用してみてください。
おわりに ~交渉を控えることを控えよう~
これまで原価の上昇で大変な思いをしてきたと思います。
一方で、行政の支援もあって、社会全体の意識が変わってきました。
わたし自身も、かつては値上げ交渉に行くと、ほとんど内容を見ることなく「他から見積り取りますよ」と言われてくやしい思いをしてきました。
しかし、直近の値上げ交渉では、完全に拒絶されることはなくなりました。
満額を勝ち取れないことや、値上げの時期を遅らされることはあっても、成果ゼロということはなくなりました。
公表されているアンケートデータを見ると、交渉に挑むことを回避している事業者がまだまだ多いことが分かります。
社会の変化を踏まえれば、交渉を控える必要性は相当に低下しています。
この記事を参考にしていただき、是非、一歩を踏み出していただけると嬉しいです。
.png)