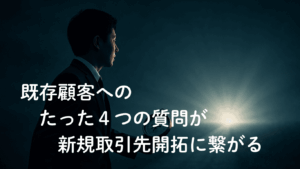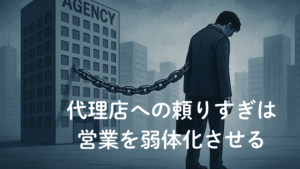「影響力の武器」に学ぶ、心理学で制する法人営業活動
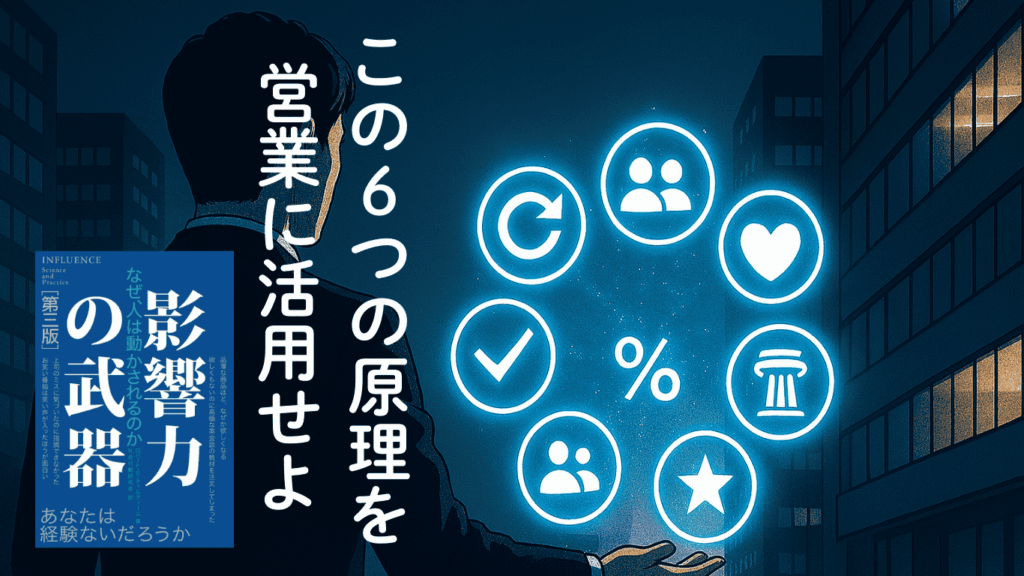
「影響力の武器」とは?
以前にナヴァル・ラヴィカントの考え方が、経営戦略にもあてはまることをお伝えしました。
>>中小企業の経営戦略にそのまま活用できる「シリコンバレー最重要思想家ナヴァル・ラヴィカント」
今回は、このシリーズとして、ロバート・チャルディーニの「影響力の武器」から学べることを抽出してみようと思います。
あなたは、こんなことを感じたことはありませんか?
「なぜ、同じ商品・同じ価格・同じ提案をしても、結果が全く違うのか?」
…それは“心理”の違いが結果を分けているからです。
私は、30歳を過ぎて物流会社に転職して、そこで初めて営業を担当しました。
当時はわからないことだらけ。
そこで、色んな人に話を聞き、あらゆる本を読みました。
その中で,今もいちばん役に立っていると思うのが今回紹介する本です。
世の中には心理学の本がたくさんあります。
けれども、それらは非常に難解で、日常の生活や仕事に活用するのにハードルがあります。
この「影響力の武器」は、広い意味での心理学の本です。
ただ、これは学問的アプローチというよりも、実践的アプローチの本です。
だから、この本に書かれていることは、実際のビジネスシーンに応用がすぐにできます。
この本は、ともすると相手から欲しい回答をずるく引き出すという側面で紹介されがちです。確かに、悪用しようとするとそうでしょう。しかし、書かれている内容をマイルドに利用すれば、社内・社外を問わず「人と接する」仕事には応用可能です。
とくに法人営業活動に応用できるのではないでしょうか。
「影響力の武器」が教えてくれる6つのこと
「影響力の武器」は、大きくいうと6つのことを教えてくれています。
①返報性の原理~いただいたらお返しをしないと~
先にこちら側が相手になにかを貢献すれば、相手はそれに対してお返しせざるを得ない。
こういう感情は、日本特有のものではないんですね。
たとえ、価値の低いものでも、必要としていないものであっても。
人は何をしてもらったら、相手にお返しをしないと気持ちが悪いようです。
これは、モノや情報をもらう場合だけでなく、相手の頼みを断った場合もあてはまります。
断ることによって、相手はあなたに「譲歩する」という貢献をしてしまっているわけです。
だから、次に小さな頼み事がなされると、あなたは断りにくくなってしまいます。
「利益は後で、奉仕が先」「損して得とれ」
何となく、日本人である私たちには身近で理解しやすい感情ですよね。
先に何かを渡してくる人には、注意が必要です。
②一貫性の原理~自分の言ったことは否定できない~
人は、自分がいったん口にしたことを否定することを躊躇します。
自分自身のなかの論理的整合を気にする、ということでしょうか。
言われてみると、こういうテクニックを使っている人がいます。
保険の営業マンです。
グラフに示された保険商品。Aの商品は得になり、Bの商品がそうではないことは明白。
それでも、聞いてきます。「●●さんだったら、どちらを選びますか?」
答えは決まっているので、「そりゃぁ、Aですよね」
こうして小さな「yes」を自ら重ねていって、自分が言ったことを否定しにくい状態になっていきます。
③社会的証明~みんなで渡れば怖くない~
人は、他人が「良い」と言っているものを「良い」と思う傾向がある。
行列のできているお店だから、良いお店だと思う。
みんなが通っているお店だから、自分も通いたい。
人間は社会的な生きものなんですよね。
みんなが同じ行動をとっていると、それが正しいかどうかという論理的思考を働かせる前に、無意識に同じ行動を取ろうとしています。
この原理が応用されているのが、インターネット上のレビューです。
星が多い商品、評価の高いお店は、無意識のうちに「良い」と認識しますよね。
本当はそれぞれの好みもあるわけで、自分にとって「良い」とは限りません。
それなのに、「みんなが渡っている」証拠を提示されると、それを信じたくなってしまう心理が働きます。
④好意~好意を受けると好意をもつ~
人は、自分に好意を寄せてくれている人に対して、好意をもちやすい。
理解をしてくれたり、評価してくれる人のことを、無意識のうちに好きになっていませんか?
少しシーン違いますが、相手に対して反論するときにも同じようなことが起きます。
いきなり間違いを指摘すると相手は反発しますが、「たしかにそのとおりだよね。ただ…」とやるだけで相手の反発は和らぎます。
⑤権威~形から入ることの効果~
人は、権威を象徴するものを目にすると、権威を感じてします。
医者と白衣、弁護士とバッジ。
よく仕立てられたスーツ、きれいに磨かれた靴、派手ではないが高級感のある時計。
そんなビジネスパーソンが目の前に現われると、自然と相手を立派な人だと感じてしまう。
逆にいえば、自分自身が権威を象徴するものを身につけたり、権威ある存在との交友関係があることを示せば、相手に対して権威を感じてもらえるということです。
⑥希少性~少ないことは良いことだ~
古今東西、手に入りにくいもの、数少ないものは価値が高い。
「残りわずかです」
「お申込みは本日まで」
こんな言葉を聞くと、行動を起こしたくなってしまうのが人間の性。
残りが少ないことを演出することで、行動をさせやすくなるわけです。
人は、希少性が高い状態になると、そのこと自体に価値を感じるのでしょう。
6つの原理を営業活動に応用してみる
さて、これらの原理を営業活動に応用するとどんなことができるでしょうか?
私が実際にやってきたことを例に、具体例を挙げてみます。
①返報性の原理の応用
ここぞという顧客に対しては、こちらからどんどん情報を提供していくべきです。
求められなくとも、他社との比較資料など先方の社内検討材料になるものを提供していく。
手土産をもっていく機会もおおいですよね。
持って行った際には、帰り際ではなくて冒頭に渡す。
ホームページで継続的に有益な情報を提供しましょう。外部委託の際の注意点や業者選定のポイントなど。
こうすることで、自然と相手にお返しをしたくなる気持ちになり、相手を信頼する気持ちに繋がるのではないでしょうか。
②一貫性の原理の応用
これは保険の営業マンの例と一緒です。
提案の際には、プランを3つ示す。
その中から、「もしもこの中から選ぶとすれば、どれを選びますか?」と選んでもらいます。
「もしも」であっても、大抵の場合は選んでくれます。
そうしたら、こう聞いてみます。「どうしてそれを選んだのですか?」
すると、頭で考えながらもその理由を述べてくれます。
このロールプレイングによって、相手は自分自身を説得するわけです。
③社会的証明の原理の応用
これも活用できますよね。
「他のお客様も、こうしています」
「先日のお客様は、このようにしていました」
こう言うことによって、それとなくこちらの希望している方向性を示せます。
こういう言い方だとあまり強引さはないので、嫌な感じがしないですよね。
とくに条件面の細かいところで、選択肢があるけれども「売る側としてはこうしてほしい」と思っていることを誘導するには便利です。
④好意の原理の応用
一度提案した案件で、その後に動きがないとき、「その後、どうですか?」とストレートに聞いてしまう営業マンを見かけることがあります。
こういうアプローチをしてしまうと、数回目で連絡がつかなくなります。
そんなとき、こう言ったらどうでしょうか。
「社内で検討する際に、足りない資料があれば作りますよ」
「●●さんが、色々大変なのではないかと思って」
相手からすると自分のことを心配してくれている、と感じるはずです。
このアプローチだと、さすがに連絡がつかなくなる事態はありません。
⑤権威の原理の応用
これは、自分のことをその道の「専門化」「プロ」であると相手に感じてもらうということです。
そのためには、資格や外見もありますが、私自身は過去に担当した案件を使います。
それも、相手がよく知っているような企業。
「私が先日担当した●●社さんでは…」
こうして控えめに伝えるだけで、相手にはあなたの専門性や経験が伝わります。
⑥希少性の原理の応用
さきほど、提案後に動きがない案件の確認の仕方に触れましたが、この希少性もそのシーンで使えます。
繁忙時期に入る頃、連絡をとります。
「現場のキャパシティがいっぱいになる可能性が高いので、もし御社がご希望ならば先に押さえます。」
こういう伝え方をすると、「煽り」ではなく自然に伝えることができ、アクションに繋がるケースがあります。
まとめ
どうでしたでしょうか?
営業活動においてそのまま活用できそうなことも多かったのではないでしょうか?
営業活動がなかなか成果に繋がらないとき、「影響力の武器」を思い出してみると改善のヒントが見つかるのではないでしょうか。
.png)