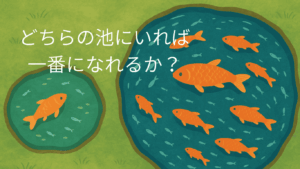採算管理における”共通のモノサシ”の重要性~倉庫業・運送業・作業請負業のための実用的な管理手法~
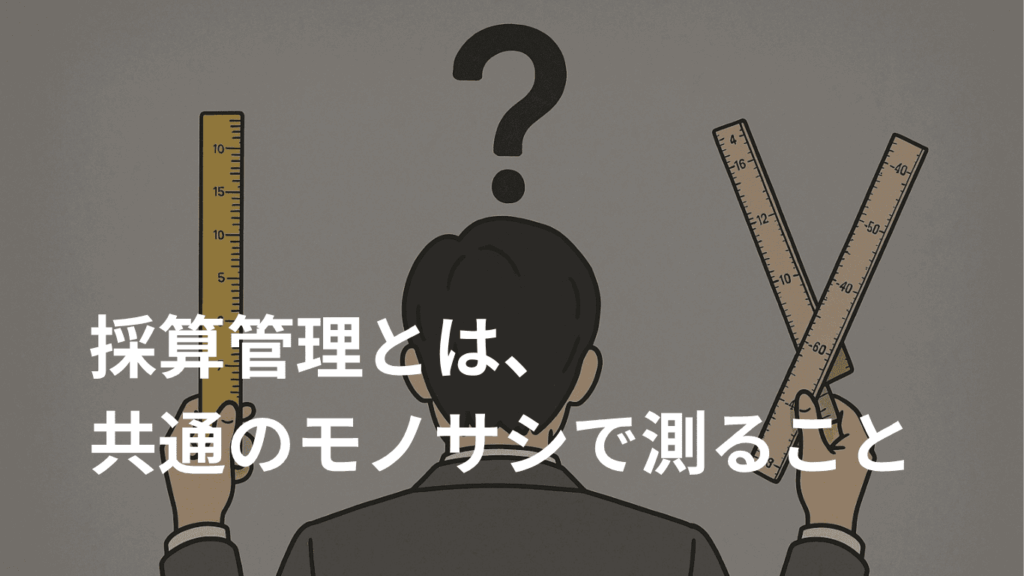
採算管理は、価格転嫁を成功させるための前提条件
前回の記事で「価格転嫁」についてお話ししましたが、今回はその一歩手前のお話です。
仮にあなたの会社で、価格転嫁による値上げ交渉を実施するとして、どの顧客の価格をどれだけ上げる交渉をするべきか、すぐに判断できますか?
この質問に即答できなかった方は、ぜひこの記事を読み進めてください。
価格転嫁の判断をするには、日ごろからの採算管理がどうしても必要なんです。
採算管理とは「儲かっているかどうか」を判断できる状態のこと
採算管理という言葉、よく耳にしますよね。
でも、その意味を自分の会社に置き換えてみたとき、「うちはちゃんとできてる」と胸を張って言えるでしょうか?
ここでいう採算管理とは、「儲かっているかどうかを、案件別・顧客別に判断できるようにすること」です。
会社全体で利益が出ているかは、損益計算書を見れば分かります。
でも、それだけではどの顧客が利益に貢献していて、どの案件が足を引っ張っているのかは分かりませんよね?
実際に私が支援に入った中小企業でも、「あの会社の仕事は儲かっている」ということだったのに、細かく見ていくと全く利益が出ていない案件が混在していました。
採算は“動く”もの。だからこそ、定点観測が必要なんです
案件のスタート時には、原価を計算して決めた価格。でも、時間が経てば状況は変わってきます。
人件費、燃料費、資材費が上がる。
取扱数量が減って固定費の比率が上がる。
そんな変化があるたびに、案件や顧客の採算性も変化します。
だからこそ、状況が変わったときにすぐに分かるように、普段からの定点観測が重要になります。
一度だけのチェックでは足りません。
継続的に見ていくことで、手遅れになる前に手を打てるようになります。
数字を出しても「それで、これって良いの?悪いの?」というモヤモヤ
ここまでで、「じゃあ、うちも顧客別に利益を出せるようにしよう」と思ってくれた方もいるかもしれません。
実際にそのような企業も増えてきました。案件ごとに売上と原価を紐づけて、利益額や利益率を出す。
ここまではOK。でも、ここで新たな悩みが出てくるんですよね。
「利益率5%って、良いの?悪いの?」「利益額300万円って、評価すべきなの?もっと改善すべきなの?」
判断材料がないと、数字を出してもどう評価すればいいのかが分からないんです。
同じモノサシで測る。「原単位管理」が突破口です
ここで重要になるのが「原単位」という考え方です。
つまり、すべての案件・顧客を同じモノサシで測れるようにすること。
こんな基準で揃えていけばいいでしょう。
- 運送業であれば、「走行1kmあたり」
- 倉庫業であれば、「保管面積1坪あたり」
- 作業請負業であれば、「作業員の稼働1時間あたり」
このように共通の基準(単位)で売上・原価・利益を見ていけば、案件ごとの採算比較ができるようになります。
たとえば、運送業で走行距離が1500kmで売上が300万円なら、1kmあたりの売上は2000円。
燃料代、油脂代、尿素代、車検・整備代、車輌代、人件費などの原価もすべて1kmあたりに換算して、同じく比較。
このとき「1kmあたり利益が500円出ている」「いや、こっちはマイナス200円だ」となれば、優先して見直すべき案件が分かりますよね。
目標となる”単位あたり利益”を定めれば、価格転嫁の基準になる
さらに一歩進んで、会社として「このくらいの利益を出すべきだよね」という水準、つまり目標となる”単位あたり利益”を定めておくと、判断が一層スムーズになります。
たとえば、間接費や投資回収などを踏まえて、「1kmあたり500円の利益が必要」と定める。
そうすると、「今のこの案件は400円だから不足してる。じゃああと100円値上げ交渉しよう」という判断が自然にできるようになります。
これは、単なる感覚や印象ではなく、“数字に基づいた根拠ある判断”ができるようになるということなんです。
粗くていい。まずは始めることが大事
「そんな細かい数字まで管理できないよ」という事情もあるかと思います。
たしかに、あまりに厳密にやりすぎると、現場の負荷も上がってしまいますよね。
大事なのは、“完璧にやること”ではなく、“比較可能な数字を揃えること”。
ある程度の粗さでも構わないので、まずは共通の単位で売上・原価・利益を出してみる。
ここからで十分なんです。
最初から100点を目指さなくてもいい。60点でも比べられる仕組みを持てば、改善のサイクルは回るようになります。
採算の見える化で、意思決定が強くなる
採算が見えると、値上げ交渉や撤退の判断など、経営のあらゆる場面で“強い意思決定”ができるようになります。
「うちの会社にとって、この案件は残すべきか、撤退すべきか」 「新規案件の条件交渉、どこまで譲れるか」
こうした判断の精度とスピードが格段に上がるんです。
私もこれまで、物流業や中小企業のコンサル支援の現場で、何度もそういった“迷い”の場面に立ち会ってきました。
でも採算が見えている会社は、やはり意思決定の確信度が違います。
最後に:採算管理は経営の質を高める
ここまで読んでいただいたあなたなら、もうお分かりですよね。
採算管理とは、単に利益を見えるようにすることではありません。
「会社の未来を決める判断」に、確かな根拠を与えることなんです。
物流業、倉庫業、作業請負業という業種は、どうしても利益構造が見えにくくなりがち。
だからこそ、「基準を揃える」ことがとても重要になります。
完璧でなくてもいいです。
まずは、あなたの会社なりのモノサシをつくることから始めてみませんか?
あなたの会社の“本当の強さ”が、そこから見えてくるはずです。
.png)