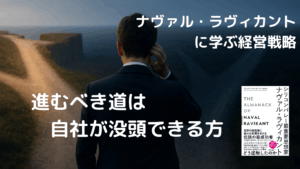中小企業のための価格転嫁交渉の実践方法
~中小企業・物流業・運送業・倉庫業が「いま」やるべき値上げ交渉のポイント~

こんにちは。
人件費、燃料費、資材費など、あらゆる費用が上昇しています。
今日は、原価上昇への対策として真っ先に考える必要がある「価格転嫁」について、具体的な進め方や考え方を一緒に整理していきたいと思います。
「価格転嫁」「値上げ交渉」と聞いて、あなたはどんな印象を持ちますか?
「難しい…」
「取引を打ち切られたらどうしよう…」
「どうやって根拠を示せばいいか分からない…」
そんな風に感じている方も多いのではないでしょうか。
実際、倉庫業・運送業・作業請負業のような中小企業の現場では、価格転嫁がうまく進められず、利益を圧迫されているケースも多く見られます。
でも、以前に交渉をして上手くいかなかった経験があったとしても、相当時代が変わってきています。
いまは、あなたの会社がしっかりと「交渉」すれば、値上げを受け入れてもらえる環境が整ってきています。
私自身もこの3年ほど、実際に自分の事業で値上げ交渉をしてきましたし、他の事業者さんの交渉支援もやってきました。
その経験を通じて感じているのは、以前と比べて「値段の話がしやすくなった」ということです。
昔は、値上げの話を持ち出すと「見積もりを出してもいいけど、相見積もり取りますよ」なんていう牽制がよく返ってきましたよね?
でも、いまは状況が大きく変わっています。
では、どうやって価格転嫁交渉を進めていくべきか、一緒に整理していきましょう。
いま、価格転嫁がしやすい理由
まず最初にお伝えしたいのが「いまを逃す手はない」ということです。
あなたもご存知の通り、原材料費、燃料費、光熱費、人件費…。あらゆるコストが上がっていますよね。
特に物流業界では、2024年問題の影響もあって、運送業の9割近くの事業者がすでに値上げ交渉に成功しているというデータもあります。
これまでは「値上げ=悪」と捉えられがちでしたが、今は「値上げは仕方がない」そんな空気が世の中に広がっています。
このタイミングで行動を起こせば、あなたの会社も確実に利益改善につなげることができます。
価格転嫁交渉の最大のボトルネック
では、なぜ多くの中小企業の価格転嫁が進まないのでしょうか?
一番大きな理由は「交渉することを最初からあきらめてしまっている」ことです。
「どうせ無理だろう」「言い出したら取引が減るかもしれない」
そんな不安が先に立って、実際の交渉まで踏み出せないパターンがとても多いからです。
でも、ここでしっかり声を上げない限り、あなたの会社の利益は守れません。
そして、いまならば交渉のハードルは確実に下がっています。
そのチャンスを逃すのは、もったいないですよね?
個別見積りの場合の進め方
倉庫業・作業請負業などでは、個別見積りのスタイルが多いですよね。
この場合、価格転嫁を成功させるカギは「根拠をしっかり示すこと」です。
ここで重要なのが「相手も、値上げを飲まざるを得ないことは分かっている」という点です。
では、なぜ渋られるのか?
それは「社内を説得する材料」が不足しているからなんです。
取引先の担当者も、あなたの会社との関係を積極的に壊したくはありません。
人は、「今のまま」を維持しようとする「現状維持バイアス」をもっています。
でも、相手の担当者にも、上司や経営陣への説明責任があります。
そのためには、「価格変更の根拠」が必要です。
相手の担当者は、あなたが価格変更の根拠を示してくれることを待っているわけです。
ポイントは、案件ごとの細かな原価ではなく、一般的な世の中のコスト上昇を根拠にすることです。
案件ごとの細部に踏み込むと、かえって現状の単価の妥当性の議論になりかねません。
だからこそ、透明性の高い「公的データ」を活用しましょう。
根拠として使える代表的なデータ
「具体的に、どうやって根拠を用意するのか分からない」という声もよく聞きます。
以下のようなデータは、簡単に調べられますし非常に有効です。
● 軽油価格・ガソリン価格の推移(経済産業省・資源エネルギー庁「石油製品価格調査」)
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/index.html
● 最低賃金の推移(厚生労働省が平成14年からの都道府県別推移を公表)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001309125.pdf
● 輸送コスト(国土交通省の「標準運賃」の推移)
各地のトラック協会の資料が参考になります。
● 電気代の統計資料(電力自由化でまとまった統計がなくなりました)
一般社団法人エネルギー情報センターの統計情報
https://pps-net.org/statistics
● その他の費用(日銀の企業物価指数)
https://www.boj.or.jp/statistics/pi/cgpi_release/
こういった資料は、行政や自治体が出しているものなので、誰もが納得しやすい透明性があります。
たとえば、契約締結時の軽油価格が1リットルあたり100円だったのに、いまは120円になっている。
この場合、20%のコスト上昇です。
この上昇率を、もともとの単価に掛け合わせる形で価格改定の提案をする。
これが、相手方が社内で承認を得やすい、理屈に合ったアプローチなんです。
さらに、こうして「根拠ベース」で価格設定しておけば、今後またコストが上がったときにも、再度の値上げ交渉がスムーズにできます。
私自身も、そういった考え方で継続的に価格見直しを実現してきました。
ちなみに、運送会社の「原油サーチャージ」のように、原価が上昇したら価格も自動的に上昇するという条項を契約に織り込むケースもあります。
この場合には、軽油価格連動型にしてもいいですし、最低賃金連動型にしてもいいです。
毎年一定率が上昇するという契約をしているケースもあります。
このあたりは取引先との関係などに応じて、使い分けていけば良いかと思います。
メニュー料金の場合の工夫
メニュー料金(パッケージ料金)の場合、単純に料金表の価格だけ上げると、悪目立ちしてしまうおそれがあります。
そこでオススメなのが「新メニューの設定+移行の促し」です。
具体的には、こういう順序です。
① 現行メニューは半年後に廃止するとアナウンスする
② 新しいメニュー(価格転嫁を反映したもの)を用意する
③ 移行を促しつつ、既存顧客にも段階的に適用していく
この方法なら「古いものをなくす」という理由付けができるため、自然と新料金への誘導がしやすくなります。
ポイントは「準備期間」と「丁寧な説明」です。
突然の強制移行はトラブルの元になるので、一定期間の猶予を設けつつ、十分に根拠資料を提示しながら進めていきましょう。
価格転嫁は、利益改善の最優先策
最後に強調しておきたいのが、価格転嫁による値上げは「利益がそのまま増える」数少ない施策だということです。
新規開拓やコスト削減と違って、既存の取引をベースに利益率を改善できるのが魅力です。
とくに今は、社会全体が値上げを受け入れる空気感ができています。
この波に乗らない手はありません。
あなたの会社も、以下のステップを意識して、今すぐ行動を始めましょう。
✔ 自社のコスト上昇を整理する
✔ 行政・業界団体のデータを揃える
✔ 価格転嫁の根拠資料を準備する
✔ 丁寧な説明を心がけて交渉する
本当はもっと踏み込んで、原価上昇を示す資料の作り方、交渉の方法なども詳しくお伝えしたいところなのですが、今回の記事ではここまでとさせていただきます。
中小企業の物流業・運送業・倉庫業にとって、このチャンスを逃すと、次はいつ来るか分かりません。
いまこそ、あなたの会社の利益を守るために、確実な価格転嫁を進めていきましょう。
.png)