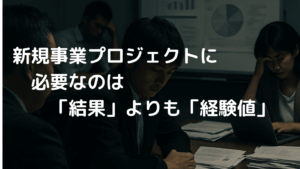中小企業がいつも忙しい本当の理由と、その対策方法 ~人手不足は原因ではなく結果~
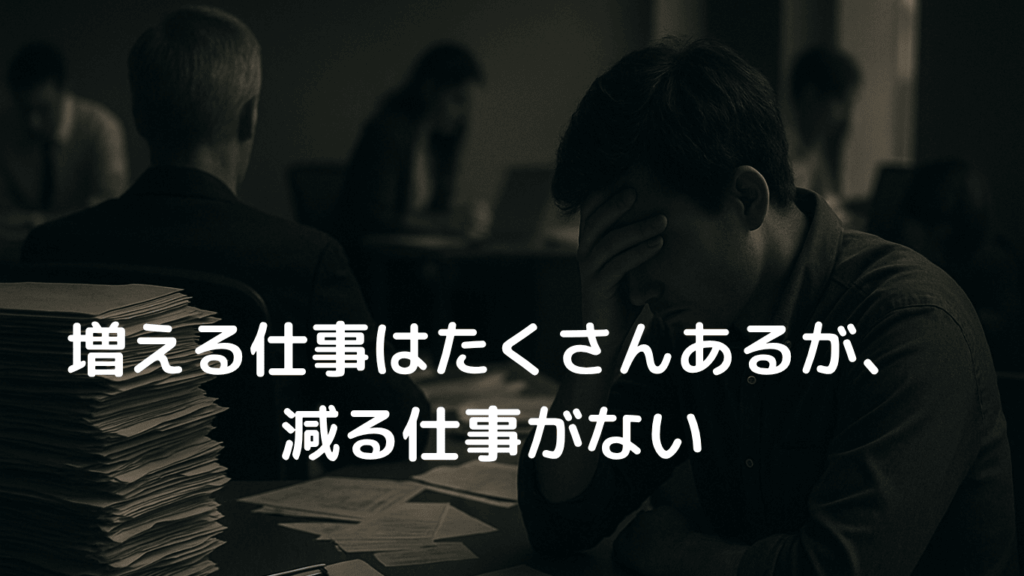
全業種共通の課題、「人手不足」
私は、仕事柄、中小企業の経営者とお話をする機会が多くあります。
みなさん口を揃えたように話される課題が、「とにかく忙しすぎる」ということ。
そして、その原因として挙げられるのが「人手不足」です。
確かに、最近はどの業界でも人手不足が大きな課題になっていますよね。
しかし、忙しさの原因は、本当に「人手不足」なのでしょうか?
忙しさが増していくメカニズム ~わたしの経験~
私は長年、新規事業開発と新規開拓営業をやってきました。その際に毎回直面することがあります。
ターゲットリストを作成して、アプローチしていく。
当初に想定したような成約数に至らない。
目標に到達するよう、さらに力を入れていく。
思ったように結果が出ないと、いろいろな意見が出てきます。
「ターゲットをずらした方が良い」
「トークスクリプトを変えた方が良い」
「伝手を探した方が良い」
とくに意見を出したのが偉い人であればあるほど、無視するわけにはいきませんよね。
それらの偉い人の意見に引きずられて、次第にやるべきことが膨れ上がっていきます。
そして、やがてどれもが中途半端な活動になっていきます。
こんな経験は、あなたの会社でも一度はしたことがあるのではないでしょうか。
忙しい会社は、やめる仕事が決められない
実は、中小企業がいつも忙しい理由がここに潜んでいる、と私は考えています。
やることが増える一方で、どれもが中途半端になってしまっている。
そのような虫食いで中途半端な状態から脱しないといけません。
そのためには、どうすればよいのでしょうか?
シンプルなことです。
やめるものを決めれば良いのです。
何をやめるか?
それは、結果に繋がらない行動をやめるです。
当たり前のことなので、多くの方は否定しないと思いますし、すでに分かっていると思います。
ですが、どこの組織でもこれができなくて悩んでいるのではないかと思います。
忙しい会社ほど、やめる仕事が決められないのです。
やめる仕事を決めるのは、人の意見ではなく客観的なデータ
なぜ、やめる仕事が決められないのでしょうか?
その理由の大半は、何が結果に直結するかが分かっていないからです。
だから、効果の乏しい仕事に人手を割いてしまう。
誰かの意見が正しいかどうかを判断できないから、取りあえず実行してしまう。
ひとたび実行すると、なかなかやめられない。
その結果、人手不足という結果が生じてしまう。
この悪循環から逃れるためには、人の主観的意見ではなく、客観的なデータにもとづいて意思決定することです。
意見を取り入れてみたところ、アポ取得率が上がった。それならば、継続していこう。
しかし、逆に成約率が下がった。それならば、直ちに中止だ。
複雑なものは分解して単純化する。
分解された単位で、客観的なデータに基づいて意思決定していけばいいのです。
データを取ることは、難しいことではない
「データを取得するためにはシステムが必要では?」
「データを分析するには時間と労力が必要では?」
あなたの頭には、そんな心配がよぎったかもしれません。
でも、心配はいりません。
プロセスを大まかに決めて、そのプロセスごとに歩留まりを測っていくだけで大丈夫です。
ポイントは、あまり細かくしすぎないこと。
アクションに結び付かない細かさは、事務を煩雑にするだけです。
例えば、営業プロセスならば、「ターゲットリスト」、「アポ取得」、「提案・見積」、「内定・成約」という4段階の件数管理で十分だと思います。
それが把握できる仕組みをつくってみてはどうでしょうか?
高度なシステムは必要ありません。エクセルでも十分でしょう。
このようにしてデータを把握することで、色々なことが見えてくるはずです。
もしも、トークスクリプトを変えてアポ率が下がったならば、それは元に戻すべきだ。
もしも、提案の仕方を変えて内定率が下がったならば、それは元に戻すべきだ。
そうすれば、確率の低い行動が駆逐されて、生産性が上がっていくはずです。
こういうやり方ならば、意見を出した人も納得すると思いませんか?
(そもそも、意見を出した人はそこまでこだわりがないのに、意見を聞いた側がそれを絶対視することは、どの組織でも起きているでしょう)
まとめ:人手不足は、仕事のやり方の結果と考える
中小企業は、いつも忙しい。
どこへ行っても「人手不足」が課題として叫ばれています。
もちろん、少子化や働き方改革などの社会の変化は、人手不足と無関係ではありません。
しかし、そういった社会の変化は、残念ながら変えることができません。
「自社の努力で変えられること」に目を向けて見る方が、少しでも現状を良くしていくことに繋がります。
そういう視点でいくと、「人手不足」は忙しいことの原因なのではなく、自社の仕事のやり方の結果であると考えるべきではないでしょうか?
やることを絞る。それは、何が有効で、何が無駄なのかを客観的に把握することから始まります。
まずはプロセスをざっくり分解して、数値を把握することをやってみませんか。
.png)