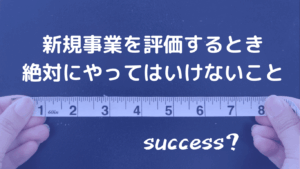サービスが顧客に刺さるために、やってはいけないこと
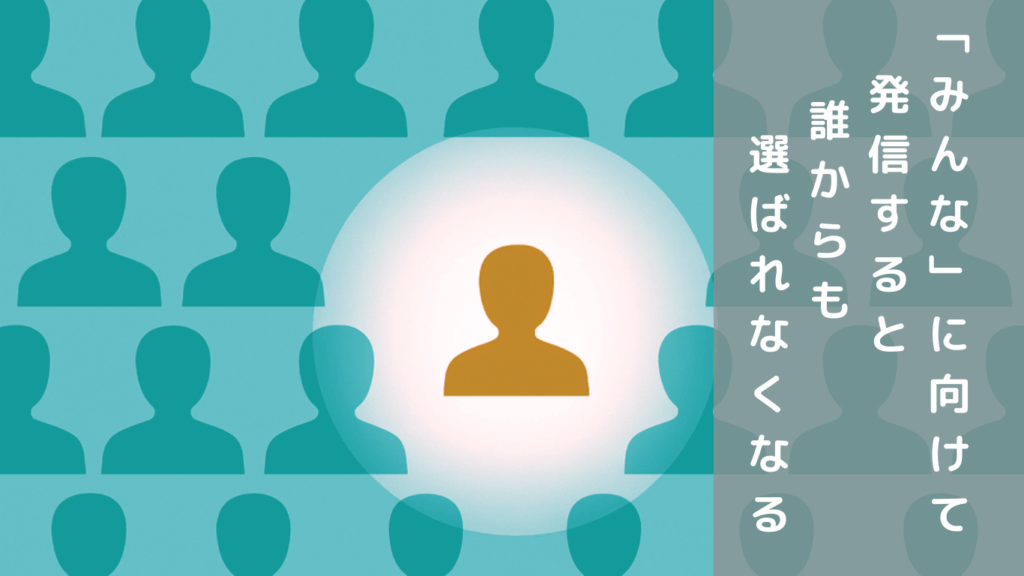
なぜ、多くの新サービスは「響かない」のか?
「このサービスなら、きっと多くの人に喜ばれるはずだ」
新しいサービスを考えるとき、そんな期待に胸を膨らませた経験はないだろうか。
だが、いざ世に出してみると、思ったより反応が薄い。売れない。刺さらない。
これは決して珍しいことではない。むしろ、多くの新サービスが陥る典型的な失敗パターンである。
その原因は、実にシンプルだ。
ターゲット設定が「抽象的すぎる」のである。
抽象的なターゲット設定が生む「誰にも刺さらない」悲劇
ターゲットを広げれば広げるほど、市場は大きく見える。
たとえば、「中小企業の経営者向け」と設定すれば、対象は数えきれないほど存在するように思えるだろう。
法人なら業種・規模、個人なら年齢・性別・地域などをざっくり決める。
こうして抽象的に設定すると、「たくさん売れそうだ」という幻想を抱きがちだ。
しかし、現実はその逆である。
抽象的なターゲット設定は、「自分にぴったりだ」と感じる人を生み出せない。
結果として、誰にも深く刺さらないサービスになり、市場から埋もれてしまうのである。
人は「自分ごと」でしか動かない
人が本当に財布を開くのは、「これは自分に必要だ」と感じたときだけである。
それは、業界全体の課題や、世代全体のニーズとは関係ない。
あくまで、「自分」や「自社」という具体的な単位での評価なのだ。
たとえば、書店に並ぶビジネス書を思い浮かべてほしい。
「事業成長の方法」という漠然としたタイトルよりも、
「40代経営者のための事業成長の方法」という本のほうが、はるかに手に取りたくなるはずだ。
なぜなら、「これは自分に向けたものだ」と直感的にわかるからである。
サービスも同じである。
誰に向けたサービスなのかを具体的に設定しなければ、そもそも興味を持ってもらえないのだ。
ターゲット設定の極意:「たった一人」を描き切れ
では、どうすれば顧客に刺さるターゲット設定ができるのか。
答えは明快である。
たった一人のユーザーを想像すること。
法人向けサービスであっても、会社そのものをターゲットにするのではない。
その会社の中にいる、具体的な「個人」を想像するのである。
たとえば──
- 業種:二次請けの作業会社
- 規模:社員30名の地方中小企業
- 立場:50代の二代目経営者、営業中心で現場は任せきり
- 状況:作業ミスが続いていて、顧客からのクレームが増加している
- 課題:作業ミスの原因がつかめていないので、手を打てない
ここまで具体的にイメージを作れば、自然と「この人にとって必要なものは何か」が見えてくる。
それが、サービス設計、訴求メッセージ、オペレーション設計すべての芯になるのである。
「絞り込み=市場縮小」ではない
ここで、「そんなに絞ったら売れなくなるのではないか」と不安に思う人もいるだろう。
だが、心配は無用である。
むしろ、ターゲットを具体化するほど、周辺の似たような人たちにも自然とメッセージは伝わっていく。
誰にも刺さらないサービスより、特定の誰かに強烈に刺さるサービスを作る方が、はるかに成功確率は高いのだ。
中途半端に広げて、誰の心にも響かないものを作るくらいなら、特定の誰かに「これだ!」と思わせるものを作るべきである。
中小企業こそ、「一点突破」を目指せ
資本力もブランド力もある大手企業とは違い、中小企業は広く浅く勝負しても勝ち目がない。
勝つためには、「この領域なら負けない」という一点突破を目指すしかない。
特に、倉庫業や作業請負業といった現場ビジネスの世界では、マーケティング視点が薄い傾向がある。
だが、新規事業や新サービスを立ち上げるならば、ここで述べた「ターゲットの具体化」は絶対に欠かしてはならない。
抽象的な「お客様全般」ではない。
顔が思い浮かぶ「たった一人」のためのサービスを作るのだ。
刺さるサービスを作る覚悟を持て
サービスが本当に顧客に刺さるかどうかは、準備段階ですでに決まっている。
ターゲットを具体化できるか。
誰か一人に対して、全力でサービスを設計できるか。
この覚悟を持てた者だけが、希少性の高い、価値あるサービスを生み出せるのである。
市場に埋もれるか、市場に光るか。
その分かれ道は、今この瞬間、ターゲット設定の精度にかかっている。
ここで手を抜くな。
ここに命をかけろ。
.png)